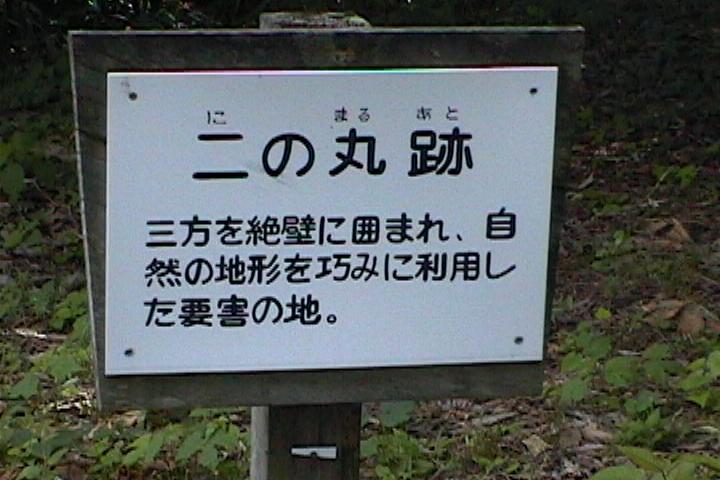
|
|
七尾城跡(ななおじょうせき)
1398年に畠山満則(はたけやまみつのり)が築いたのが七尾城です。
それから180年間栄(さか)えましたが、上杉謙信(うえすぎけんしん)に攻(せ)められ、ほろびました。

|

|
|
金沢城(かなざわじょう)
金沢城は、16世紀、一向宗の尾山御坊からはじまりました。
そして、前田利家が金沢城に入り、本格的な城にしました。
金沢城は、これまで「金沢城址」(かなざわじょうし)と呼ばれてきましたが、平成13年12月より、「金沢城」と呼ぶように決まりました。

|

|
|
石動山(せきどうざん)
能登と富山の境に位置する標高565メートルの山が石動山です。
昔、この山一体には石動山本社を中心とするお寺があり、気多大社(けたたいしゃ)や総持寺(そうじじ)と並ぶ、能登の信仰の中心地でした。

|

|
|
御経塚遺跡(おきょうづかいせき)
野々市町にある、縄文時代の集落跡です。
昭和30年から発掘(はっくつ)が続き、今では28の住居跡が確認されています。
遺跡の南側には史跡公園があります。また、公園の横には収蔵庫(しゅうぞうこ)が設けられ、土器や石器などが展示されています。

|

|
|
大海西山遺跡(おうみにしやまいせき)
高松町大海にある、弥生時代の高地性集落跡です。
卑弥呼(ひみこ)の時代、争いごとから逃(のが)れるため、人々は生活の不便な高い山の上に村を作りました。
これが高地性集落と呼ばれる遺跡で、大海西山遺跡はその代表的なものです。

|

|
|
津幡町加茂遺跡(つばたまちかもいせき)
津幡町加茂・舟橋地内にある加茂遺跡です。
大量の土器や木製品のほか、和同開珎銀銭(わどうかいちんぎんせん)などが出土しています。
この遺跡からは墨書土器(毛筆で字の書かれた土器)が200点以上も見つかりました。「英太」「正月」などの文字が書かれていました。

|

|
|
雨の宮古墳(あめのみやこふん)
眉丈山系(びじょうざんけい)の尾根筋(おねすじ)に散在(てんざい)する古墳群です。
北陸地方最大の前方後方墳(ぜんぽうこうほうふん)や前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)があります。

|

|
|
上山田貝塚(かみやまだかいづか)
宇ノ気町にある貝塚遺跡です。
この貝塚は、昭和5年に石川県で最初に発見された貝塚として有名です。
イシガイやオオタニシなどの淡水産貝類とフナなどの魚骨が圧倒的に多いのが特ちょうです。

|

|
|
末松廃寺跡(すえまつはいじあと)
野々市町末松にある寺院跡です。
末松廃寺を建てたのは、古墳時代後期にはすでに北加賀地方を支配(しはい)していた道君(みちのきみ)の一族と考えられています。

|
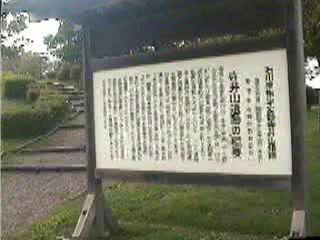
|
|
寺井山遺跡(てらいやまいせき)
寺井町にある遺跡です。
この遺跡は、古墳時代の祭祀(さいし)遺跡と墳墓(ふんぼ)が同じ丘陵上に営(いとな)まれた全国でも例の少ない遺跡です。

|
 しせき
しせき  しせき
しせき