令和4年10月20日 |
|---|
吾輩は猫である 前回更新して以来、5ヶ月ぶりの『ちょっとひとこと』です。 「今は“ちょっと”昔」ですが、6月から「おやじのA」が秘密基地で雄猫を飼い始めました。【令和3年11月8日『DIY』参照】 ふらっとやってきた生後1ヶ月くらいの野良猫で、初対面から人なつこく、餌を与えるとおいしそうに食べたそうです。 病院で必要な検査と処置を受け、おやじのガレージに4階建てのケージを買ってもらって、猫はめでたくおやじのペットになりました。 『チャ』と名付けられましたが、「茶トラ」であることがネーミングの由来だとすると、このあたりには安直さが漂っています。 今ではずいぶん大きくなり、少々肥満気味なのですが、これは「飼い主に似る」典型であると思われます。家では犬や猫を飼わせてもらえないうちの娘も『チャ』のファンになりました。 毎日、出勤時と帰宅時にケージへ行って、「もふもふ」しながら癒やされています。 また、猫じゃらしを買って遊んで(遊ばれて)やったり、夏の暑い日には冷蔵庫で冷やした保冷剤にタオルをまいてケージに入れるなどせっせと世話をやきました。 そのせいか、娘はおやじの次になつかれています。 ときどきどこかの茶白の猫が来て、ケージの側に座ります。そんなとき『チャ』は「ウー」と警戒の声をだすのですが、 それを聞くと、娘は不審猫対応に向かうべく私をさそいに来ます。 たとえ深夜でも命令が下るので、さすがに少し閉口していたのですが、最近はあまり緊急出動がないので非常に助かっています。(T)   |
令和4年5月10日 |
|---|
仁義なき戦い 今朝、ハクビシンの被害に遭いました。昨年8月の「桃太郎」以来の、悲報です。【令和3年8月3日『鬼退治』参照】 以下、BGMに『BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY』(曲:布袋寅泰)が流れていると思って、お読みください。 被害に遭ったのは、「とちおとめ」。2018年の平昌オリンピックの時に、カーリング女子日本代表が「もぐもぐタイム」で「韓国のイチゴはおいしい」と言いながら食べていたあのイチゴです。 ちなみに、「とちおとめ」は、栃木県農業試験場で開発され、その後韓国へ流出してしまった、日本産のイチゴですからね。 今年の4月にプランターに植え付けて大切に育て、5月になってやっと実が赤くなり、そろそろ初収穫だと楽しみにしていた矢先の出来事です。 いくつかついている実のうち、赤くなっていた4個だけがきれいに食べられていました。 簡易温室の上段にのせて、カラスの対策としていたのですが、うかつにもハクビシンは想定していませんでした。 「家庭菜園あるある」なこととはいえ、イチゴを前にした娘やお母さんやおばあちゃんの笑顔を思い浮かべると、かなりくやしい出来事です。 とちおとめ4姉妹も、さぞかし無念であったろうと思います。 というわけで、今年は、ハクビシンとの対決を敢然と決意しました。取りあえず、プランターと地植えで育てているトマトの警護体制を考えておかなければなりません。 家庭菜園歴3年の叡智を結集して、来たるべき戦いに備えたいと思います。 そういえば、かなり昔の話ですが、アントニオ猪木選手との対決で話題になった「タイガー・ジェット・シン」という悪役レスラーがいました。 イチゴとは関係の無い話ではありますが、ふと思い出してしまいました。(T)   |
令和4年2月28日 |
|---|
不審人物 冬型の気圧配置が、なんとか緩んだ先週の金曜日のことです。朝起きて、新聞を取りに行くと、玄関に小型のゴミ袋がぽつんと置いてありました。 そういえば、今日はゴミの日。先だってゴミ出しの際に雪の上で転んでもがいた経験を「反省」したおばあちゃんが、たぶん昨晩のうちに置いたものです。 【2月4日『おばあちゃん、雪の日の災難』参照】 娘の出勤を見送りがてら、ちゃんとゴミステーションに出してきました(^_^)。 その日は、好物の「ドライカレーオムライス弁当」をおかあさんが作ってくれたので、とてもうきうきして早めに家を出たのですが、 5~6分ほど走ったところで、どこかのおじいちゃんが雪の歩道沿いをぽてぽて歩いているのを見かけました。 反対車線で後続車もいたため通り過ぎたのですが、「心配だなぁ」とバックミラーで確認していると、よろけて雪の上に倒れ込む姿が見えました。 そばを通る車が止まる気配は、ありません。そのとき、わが家のおばあちゃんのことが想い浮かびました。 思わず引き返して声をかけたのですが、「あんたどこの人や」と、どうも不審そうです。それで、「○○のもんやわいね」と私の在所の名前を教えて、 「家まで送るさかいに車に乗るまっしゃい」と伝えると、やっと少し安心したように、「すまんね」といいながら起き上がろうとしました。 見ると、上の薄手のカーディガンと下のスウェットパンツが雪で濡れています。体をこわばらせて震えながら、支えるためにつかんだ二の腕からも、 ずいぶん体が冷え切っているのがわかります。 言われるままに1㎞ほど車を走らせると、着いたのは老人介護施設。職員らしき人が、玄関から施設の中へ連れて入る際に「歩いてきたんですか?」と声をかけていたので、 おじいちゃんは自分の家からここへ来る途中だったようです。車に乗せた場所を考えると、すでに200m以上は歩いていたのではないかと。 きっと、リハビリのつもりで歩き始めたものの、寒さで体が動かなくなったのではないでしょうか。引き返して良かったな、と思いました。 考えてみれば、わが家のおばあちゃんのことがあったから、おじいちゃんに気を回すことができたのだろうと思います。 そして、良い気分でいつもより早めに家を出たから、引き返す心の余裕が生まれたのでしょう。これが、「縁」と言うものなのかも知れません。 ただ、今にして思えば、施設の玄関で会った職員の方も不審そうに私を見ていたのですが、事情を話す暇も無かったので....。 変に誤解されていなければ良いな....と(笑)。(T)   |
令和4年2月14日 |
|---|
大根役者 前回「雪はもう積もらないような気がする」と書きましたが、その希望的観測は見事に打ち砕かれてしまい、 その週末は、新たに積もった玄関付近や駐車場の雪を除けたり、落ちた屋根雪を崩してどかしたりしたので、背中や腰が痛くなりました。 わが家の菜園も再び雪野原となり、大根・小カブ・人参・キャベツ・白菜・ほうれん草・ネギは雪の中で出番を待っています。 もっとも、雪にあたった野菜たちはとても甘いので、こっちの「雪どかし」はそんなに苦にはなりません。 昨日、お母さんに頼まれて大根を一本収穫しました。ちなみに、当家ではブリ大根様が食卓におのぼりになることはめったにありません。 ですが、普段の「イカ大根」「鶏肉大根」そして「シーチキン大根」だってとってもおいしいのです。 また、お母さんの大根菜と油揚げの炒め物、おばあちゃんの大根ピクルス、娘の大根スティックとお味噌、私の大根おろし醤油かけご飯も、安定の逸品です。 江戸時代、芝居が下手な歌舞伎役者を「大根役者」と野次ったそうです。その言葉の由来としては、 「演技が素人のようだから」「下手な役者はおしろいをたくさんつけるから」など白さにかけたものや、 「あたらないから」という消化の良さにかけたものなど諸説あるようですが、いずれにせよ「大したやつじゃない」という意味です。 しかしながら大根は、主菜のありようを云々する西洋のコース料理に比べ、全体の調和で味わう懐石料理では大切な個性のひとつです。 そして、ブリ大根のように、そのうまみを浸み入らせることで、時に主役に取って代わる大したやつでもあります。 あったかなブリ大根が食べたくなりました。すこし節約をして、お母さんにお願いしてみようと思います。(T)   |
令和4年2月4日 |
|---|
おばあちゃん、雪の日の災難 月日が経つのは早いもので、お正月が終わったなぁと思っていたら、もう立春になりました。 天気予報では、先週から今週にかけてまだまだ「雪だるま」のマークが並んでいますが、もう積もらないような気がします。 やはり、地球が温暖になったせいか、「昔」に比べると積雪は少なくなりましたね。 私が子どもの時は、「節分」の頃にも雪が積もっていたような記憶があります。 登下校の際には、長靴で圧雪された道路を滑りながら、落ちた屋根雪の山脈をのぼりくだりしながら歩くのが楽しみでした。 もっとも、雪でスリップした車がこっちに向かってきて、軽くはねられたという経験も何度かあります(^_^)。 今は、除雪車と融雪装置のおかげで、「道路上に圧雪」というのはなくなりました。 これは車を運転する側にとっては有り難いことなのですが、歩行者は道路際に除けられた雪や融雪のための水でたいへん難儀することになります。 この件に関しては、どうも「歩行者優先」にはなっていないように思います。私も、運転の際には、気をつけてはいるのですが。 それなりの積雪があった、ある朝のこと。出勤しようと玄関を出たお母さんが、雪の上でもがいているわが家のおばあちゃんを見つけました。 「燃えるゴミの日」で、運動を兼ねて自室のゴミをゴミステーションまで運ぼうとしたらしいのですが、 歩道沿いにたまった雪に足を取られてうつ伏せに倒れて起きれなくなったとのこと。 幸いお母さんのおかげで何とか事なきを得たのですが、おばあちゃん曰く、「いちばん情けなかったのは、車が側を通るたびに頭から冷たい水をかぶったこと」だそうです。(T)   |
令和4年1月4日 |
|---|
リスクマネジメント 年末年始、いかがお過ごしでしたか? 寒波の到来による降雪があり、福岡・東京・千葉・新潟・仙台に住む大学時代の友人との情報交換によれば、 その中では私の家が一番積雪が多かったようです。ただ、日本海側の地域では早くから降雪や冷え込みへの注意喚起がなされており、 その備えがあったせいか積雪や凍結などによる大きな混乱は無かったようにも思います。 わが家では、寒波による混乱は早朝の水道の蛇口の凍結ぐらいのものでしたが、大晦日の晩に台所(ダイニング)のテレビが映らなくなるという不幸に見舞われました。 紅白歌合戦を見ながら、年越しそばを茹で始めたところだったので、家族の団らんという観点からは、非常に良くないタイミングでした。 そのテレビは十五年以上も前のものであり、画面が突然消えるという予兆現象は一ヶ月ほど前から散見されていました。 そのため、お母さんとは、「もし年末年始にテレビが映らなくなったらどうするか」と、有事の場合の手立てを話し合っていたところではありました。 テレビのシャットダウン後、かねてからの手はずどおり、私がすぐに自室のテレビの配線をはずして台所に持ち込むと同時に、 お母さんと娘が台所のテレビを別室へと撤去しました。その後、素早くアンテナ等の配線とチャンネル設定を完了し終えたため、 多くの歌手の方の熱唱を見逃すことなく、年越しそばがのびてしまうことなく、わが家は大晦日の一家団欒を回復することができました。 昨日は、お母さんと一緒にリサイクルショップを訪れ、あらかじめ目をつけていた安価なテレビを購入しようとしたのですが、 残念なことにすでに無くなっていました。ひょっとしたら、わが家と同様の不幸に見舞われたお宅があったのかも知れません。 というわけで、ネット通販で、これもあらかじめ見当をつけていたテレビを、さっそく購入しました。明日、自宅に届く予定です。 ちなみに、「この際Wi-fi接続が可能なスマートテレビを購入すればどうか」とお母さんに提案してみたのですが、 「台所のリフォームを終えたときにもっと大きな画面の立派なテレビを買う」とのことで、却下されました。 どうも、古いテレビの故障は、大規模な出費につながりそうです。(T)   |
令和3年12月24日 |
|---|
楽しく懐かしい思い出 令和3年も残すところあと数日になりましたが、「ウィズコロナ」の年末・年始のご予定はいかがでしょうか? 私は、例年の如く、 なぁーんにも予定はありません。多分、テレビで「箱根駅伝」を見るぐらいだと思います。 実は、ずいぶん長いこと陸上部の顧問をしていたこともあり、陸上競技や駅伝を見るのは好きです。 そして、時々ふとそのときのことが思い出されます。たくさんの選手諸君やマネージャーたちのことが、 今となっては、みんな楽しく懐かしく感じます。というわけで、ある高校での、思い出のひとこまを... 比較的近くの陸上競技場で記録会がある、とある日曜日の朝のことでした。選手は直接競技場に集合ですが、 マネージャーさんたちは学校に集合して氷やお茶などの準備をしていました。出発時間が迫ってきたので、 「準備はできてますか?」と確認メールをしたところ、「もう校門前で舞ってます!」と返事がきました。 そのマネさん、ちょっと「天然」なところがあったので、ひょっとしたらと思いながら校門前へ向かいましたが、 いつもと変わらず普通でした。 マネージャーは何人かいましたが、その天然マネの名前は「加藤さん」といいます。彼女はいつも献身的なマネさんなのですが、 ただ、真面目すぎて、ギャグ的な状況がわからない(気づかない)こともありました。 ある夏の日の練習中のこと、ほっと一息ついた短距離陣から、「おーい。加藤、お茶!」と声がかかりました。 遠くの方からだったので、加藤の「O」とお茶の「O」がひとつの音に聞こえたのですが、 彼女は絶妙のタイミングで「はぁーい!」と大きな返事をして、やかんを手に走って行きました。 私の頭の中には、とある5人組のうちのひとりの姿が浮かんでしまいましたが、 戻ってきた彼女は、少しはぁはぁしていたけれど、いつもと変わらず普通でした。 それでは、よいお年をお過ごしください。(T)   |
令和3年11月8日 |
|---|
DIY 令和元年の中秋に始めた、この「ちょっとひとこと」のコーナー。早いもので、開始以来、もう2年以上がたちました。 ふと思い立って読み返してみたのですが、大学時代にアルバイトでお世話になった親父さん、在所の祭り連の子どもたち、 わが家のおばあちゃんや娘、裏のO家のおばさん、お隣のおとっちゃんとおっかちゃん、たぬきとカラスとハクビシンとヒヨドリ....、 これまでにたくさんのキャラが登場しました (^_^)。 今回、ここで、一人の奇才が登場します!。自称「おやじのA」。生誕以来ほぼ半世紀、しばらく故郷を離れていた時期もありましたが、 現在は信楽の置物のような風体で、料理に裁縫、大工仕事、はては地域の伝統芸能活動まで何でもできるので、在所では圧倒的な存在感を放っています。 一度、石動山の大宮坊で白黒の法衣を着て太鼓をたたいている動画を観ましたが、ほとんど山法師のそれでした。 まあ、時にはベレー帽なんかもかぶって歩いている、「ちょい悪」です。 その器用なおやじAが、数ヶ月前に突然「来年の春に在所で居酒屋はじめます」と言い出しました。確かに、調理師免許を持っているのでけっして無理なことではなく、 風体からするとむしろ似つかわしいようにも思います。そういえば、昨年、古びた自動車小屋をDIYで修築・増築し、 愛車の他にド派手な軽トラと大型三輪バイクやらを揃えて「サンダーバードの秘密基地」の如くにしていたのですが、 何故かそこに冷凍庫などが置かれており、不思議には思っていました。 以来、おやじAは、仲の良い近所の大工Tさんと、わいわいいいながらテーブルの天板や足を作ったり椅子を削り出したりしてます。 ただし、作業時のBGMが山口百恵さんだというところが、若干おやじの年代を感じさせます。(T)   |
令和3年8月3日 |
|---|
鬼退治 わが家の家庭菜園では、ミニトマト(アイコ・千果・キャロルの3種類)をプランターで、中玉トマト(フルティカ種)と大玉トマト(桃太郎)を畑に地植えして育てています。 実は、昨年もトマトを栽培してみたのですが、ミニトマトと中玉トマトの脇芽欠きや雨よけ対策を怠ったり、大玉トマトをプランターで育てるという暴挙にでたことによって、 思い通りに収穫することができませんでした。実がはじけてしまったり、未熟な状態でだめになったり、かなり悔しい思いをしました。 今年は、昨年の反省を生かして、適材適所(?)に苗を植えつけ、こまめに整枝したり雨よけシートを張るなど手間をかけたことで、連日たくさんの完熟トマトが収穫できています。 とてもわが家だけでは食べきれず、親類縁者にお裾分けしているのですが、皆さんも「お店のものよりおいしい」と言ってくださるので、単純に自己満足しています(^_^)。 ところが、ここにきて、大玉トマトの桃太郎に「事件」発生。今朝の水やりの時に、昨夕「明朝に収穫」とほくそ笑んでいた完熟桃太郎が何者かに食べられているのを見つけたのです。 「金メダルは確実」と楽しみにしていた選手が、せっかく決勝戦まで進んだのにあっけなく負けちゃったような気分です。 畑の「防御態勢」から考えるに、犯人はカラスやタヌキではありません。おそらく、狭いネットの隙間から入り込みそれを登ることができるハクビシンの仕業に違いありません。 先日、長年放置され朽ち果てていた近所の空き家が取り壊されたのですが、それと何か関係があるのかもしれません。 今、完熟トマトの防衛策を、必死になって考えています。桃太郎に成り代わって、浮世の鬼を退治してやろうと思います。(T)   |
令和3年6月8日 |
|---|
以心伝心? お隣の家は、「おとっちゃん」と「おっかちゃん」だけの二人暮らし。ともに80歳は過ぎているのですが、まいにち畑で野菜作りに精を出していらっしゃいます。 そして、私が同じように作業をしているのを見ると、それぞれがふらっと立ち寄って、話しかけてくださいます。 おとっちゃん 「まいこと畑しとってやねぇ。おっちゃかあちゃんも畑仕事大好きやけど、わしゃ大嫌いや。 そやけど、かあちゃんなせぇちゅうさかいに、しゃぁなしにしとるがやわいね。」 おっかちゃん 「いつも精でとってやねぇ。おっちゃとうちゃんも、もうちょっとちゃんとしてくれりゃいいがに。 自分な野菜嫌いやさかいに、してくれゆわにゃ、なんも手伝いしてくれんげわいね」 とまぁ、こんなかんじです(口語訳省略)。最初は挨拶で、後はお互いの愚痴になるのが、まいどのパターンです。 ただ、二人ともかなり耳が遠く、私が話しても会話らしいものにはならないので、ほとんど大きな声で相づちを打つだけの聞き役になっています。 なので、何かを伝えるときには、身振り手振りを交えての、ちょっとした奮闘努力が必要になります(笑)。 ところが、先日、二人が一緒にサツマイモを植えているところを何気なく見ていると、特段大きな声を出しているわけでもないのに、 不思議なことに「ちゃんと会話しながらの協働作業」が成立しているのに気づきました。とても面白かったので、あとで娘に話してみたのですが、 「長年連れ添った夫婦だけが獲得できる超能力に違いない」との見解でした。 目と目で通じ合う かすかに ん、色っぽい 目と目で通じ合う そうゆう仲になりたいわ ..... 工藤静香の名曲『MUGO・ん…色っぽい』より(T)   |
令和3年5月18日 |
|---|
小学校4年生の時の思い出 小学校の時分は、学校から帰ったあと、在所のみんなでソフトボールをするのが楽しみでした。 学校にいるうちに、5年生や6年生から「広場に集合」などと伝言がきます。帰宅後は、引き留められないようにすばやく家を出て、 ドキドキしながらまっしぐらに広場に向かいます。人数の関係で、2チームに分かれて試合をすることは出来ないのですが、 守備・打撃・走塁とローテーションをしながらそれなりに楽しんでました。 ただ、たまに、私にだけ「集合」の声がかからないこともありました。 だいたいは、上級生の間で、ソフトボールではなく、学校で禁止されている遊びか大人から叱られそうな遊びが計画されたときです。 なんせ、私の母親は同じ小学校の先生だったものですから。 家に戻った後の夕飯がカレーライスだったときの幸福感は、筆舌に尽くし難いものがありました。 カレーが大好物だったので、たとえ肉やジャガイモなどの具が入っていないカレー汁だけでも、 ご飯があればそれで良いと思っていました。今でも、カレー味のカップヌードルを食べた後に、ご飯を入れておじや風にして食べるのが大好きです。 そういえば、ある日学校から戻り、夕飯を準備するおばあちゃんに献立を尋ねたところ、「今日はカレー」だということ。 「やったー」と思いながら、ソフトボールを終えたあと楽しみにして台所に行くと、食卓に並んでいたのは茶色く平べったい魚だったという、 とっても悲しい出来事があったことも覚えています。(T)   |
令和3年4月8日 |
|---|
|
『春風や 闘志いだきて 丘に立つ』(高浜虚子) 令和3年度がスタートしました。新年度を迎え、「さぁ頑張るぞっ!」「最初が肝心だ」と、 決意を新たにしている人も多いのではないでしょうか。 私は、この季節がとても憂鬱でした。自分なりに目標をイメージして頑張ろうと思っているのに、 「○○しなければならない」と勝手に目標を設定されたり、人に会う度に「頑張れ」と言われるのが苦痛だったからです。 また、自分のことを一方的に評価されるのも嫌でした。たぶん、優柔不断で腰の重い人間だった私は、 「他者から求められるもの」と「自分が出来そうなもの」との間にギャップを感じて、 それがプレッシャーになっていたのだろうと思います。 仕事などの取りかかりも遅い方でした。頭の中で「あーだ、こーだ」と悩んでばかりいて、 期限間際になって冷や汗をかくということもよくありました。やり始めればなんとかやり遂げるので、 「締め切り際の魔術師」などと自虐的に吹聴していたものです。ただ、それでは完成度の高い仕事にはなりませんし、 第一周囲にとっては迷惑この上ありません。 その後「それじゃいかん」と悔い改めた私が、折に触れて自分に言い聞かせている言葉があります。それは、『0よりは1、1よりは2』です。 特に、気乗りがせず先延ばししたいと感じているときに、自分を叱咤するために心の中でつぶやいています。 「やらないよりはまし」「ついでにもうちょっと」という、冒頭の句に比べるとかなりレベルの低いものですが、オリジナルです(笑)。私のような人間は、 一発で完成させて常に満点を得ようとするのではなく、「とりあえず荒く仕上げて少しだけでも熟成させよう」と考えるほうがうまくいくようです。 『満点なんか取らんでええねん、満天は星空だけで充分や』(明石家さんま) .....さんちゃんに、座布団一枚!(T)   |
令和3年2月15日 |
|---|
|
ある穏やかな日の「散歩」 先日、在所の門徒総代の方から、報恩講の案内を檀家に配付して欲しいと依頼されました。 案内を入れた角封筒をもらい、それには配付先リストが貼り付けてあったのですが、 お名前を見てもその場所が分からないお宅が数軒。一瞬、どうしようか...と思ったのですが、 「困ったときのおばあちゃん頼み」で、私の母親に聞いてみることにしました。 すると、さすがというか何というか、おばあちゃんは地図も見ないでその場所をすらすらと教えてくれるのです。 おかげで、すべてのお宅の位置がわかりました。ただ、少々困ったのが、昔の言葉遣い。 「オミヤサンノ ウラテノミチヲ、チョッコシ アガッタトコノ ウチヤガイネ(神社の裏側の通りを、少し山手の方に行ったところにある家だよ)」 「ハイットグチャ ミチノキワデノウテ、 アッチナホウニ アルサカイニ スグワカルワイネ(玄関が通りに面しておらず、向こうの方にあるからすぐわかるよ)」 「ソヤケド、 オオカタ、 ヘンマハ ダンモオランジヤロウ(けれども、多分、日中は誰もいらっしゃらないと思うよ)。 暖かな日で、小学生時分に友達と自転車に乗って遊び回ったことなどを懐かしく思い出しながら、のんびり歩いて配りました。 家に戻って、おばあちゃんに「さすがだねぇ、達者だねぇ」と声をかけると、「アンタ、 ワタシャ ココデ ナンネン イキトルト オモトルガイネ」...。 「85年!」とツッコミを入れようかとも思いましたが、やめました。(T)   |
令和3年1月7日 |
|---|
|
年末年始の出来事 ついこの前元号が新しくなったように感じていたのですが、あっという間に「令和3年」になってしまいました。 この年末・年始、皆さんはどうお過ごしだったでしょうか。 「出来事」と言う表現を使うと、ともすれば、「こんなことがありました」とか、「こんなことをしました」という楽しい報告(?)を期待しがちなのですが、 今年に関しては、「ありませんでした」「しませんでした」と、寂しい思いで過ごされた皆さんも多かったのではないでしょうか。 私自身は、もともと「巣ごもり」状態で年末・年始を過ごすとっても地味な人間であるため、 例年と大した変化はなかったのですが、ただ、毎年年末に開いている「班の総会」が中止になったのは、少々残念なことでした。 総会自体は会計報告と次年度の班役員や係の輪番などを確認し合うだけのものなのですが、総会後に催される懇親会で、 昔話に花を咲かせ、近況を語り合ったりするのは密かな楽しみだったからです。 実は、昨年の正月には、ちょっとした出来事がありました。元日に在所の神社へ参拝に行き、無病息災と家内安全を祈願したのですが、 家に戻ろうと車をバックさせたときに、鳥居付近の「旗を立てるポール」に車の後部を軽くぶつけてしまったのです。 ポールには全く被害はなく、車もバンパーがほんの少しだけ歪んだ程度だったのですが、昨年は、「お参りしたからそれですんだのだ」「気をつけろと神様が教えてくれたのだ」 と自分に無理矢理言い聞かせながらスタートした一年でした。(T)   |
令和2年12月10日 |
|---|
|
家族で「わいわい」 お鍋がおいしい季節になりました。家族みんなで食べる鍋料理は、格別においしく感じられるものですが、 ただ、今年は、「お店でわいわい」はとりあえず自粛、という人たちも多いかもしれませんね。 我が家は、娘・お母さん・私、そしておばあちゃんの4人暮らしです。おばあちゃんは85歳になりますが、 幸いまだ元気で、勤めに出ている私たちのために、毎日夕食を作ってくれています。 朝昼のご飯は「家で一人」なので、夕食にはみんなが揃えば良いのでしょうが、娘とお母さんは仕事で帰宅が遅く、なかなかそれも難しい状況です。 昨日は、珍しく娘が早く帰宅し、夕食の一品にとお好み焼きを作りました。そして、お母さんが朝用意してくれたキャベツのトマト煮、 私が畑から採ってきたカリフラワー・ブロッコリー・ラディッシュのサラダ、おばあちゃん得意の大根の含め煮が食卓に揃いました。 残念ながら、お母さんの帰宅は夕食に間に合わなかったのですが、3人で「わいわい」おいしく食べました。 食事後、娘とおばあちゃんでチーズケーキをシェアしました。お好み焼きのお皿に箸を使って食べてましたが、 おそらく、これ以上洗い物を増やさないぞという計略に基づいた行動だと思われます。 そのせいか、私が「カレーの鍋」に直接ご飯を入れて箸で食べても、咎められることはありませんでした。(T)   |
令和2年11月2日 |
|---|
|
「コロナに負けるな」挨拶大作戦 夏に比べると、ずいぶん夜明けが遅くなりました。以前は5時にはもう空が白んでいたのに、 曇り空だったせいか、今日は6時を回ってもまだ薄暗いままでした。 カラスたちの「ミーティング」開始時間もずいぶん遅くなり、私も、玄関先の花への水やりを、出勤前の時間帯へと繰り下げました。 先日、水やりをしていると、いつも大きな声で挨拶をしてくれる男の子が通りかかりました。 出勤のためちょうど玄関に出てきた娘と「おはようございます」と元気に挨拶を交わしていたので、 負けずに私も「おいーっす」と声をかけました。ところが、私には挨拶が返ってこなかったのです。 気になったので、「なんでだろう」と娘に尋ねてみたのですが、娘曰く、「学校にはそのような挨拶のバリエーションはないから対応はできない」とのこと。 「だって、昔土曜の夜8時からやってた番組のコントは、この挨拶から始まったのだよ」と食い下がってはみたのですが、 「それはそれ、これはこれ。昔は昔、今は今」と一蹴されてしまいました。私の小学校時代は、 友達との挨拶では普通に使っていたのだし、明朗快活で良いと思うんだけど....。 学校では「新型コロナウィルス感染予防」のために行事が中止・縮小され、子ども達はすこし元気がないという話を耳にしました。 何か、少しでも元気が出る方法は無いものですかね。ひょっとして....『もしも』.... 朝登校したときに校長先生が「おいーっす!」と迎えてくれて、クラスには「ケン坊やチャー坊」みたいなのもいて、 下校の時には担任の先生が「宿題しろよ!歯みがけよ!お風呂入れよ!....それじゃ、また明日の朝8時に全員集合ーっ!」なんて超明るい学校があったら....。 このコロナに打ち勝つアイディア、娘が帰宅したら話してやろうとも一瞬思ったのですが、『だめだこりゃ』と冷たく秒殺されそうなので、今日のところはやめておきます。(T)   |
令和2年9月29日 |
|---|
|
「成り年」と「不成り年」 我が家の畑にはイチジクの木が植わっています。かなり前からそこにあるので、老木とまではいかないにしても、 そこそこ頑張って生きてくれているイチジクくんです。昨年はちゃんとした実がならなかったのに、 今年は「成り年」のようで、たくさん実をつけてくれています。 成り年(表年)と不成り年(裏年)、面白いですね。一説には、不成り年にしっかりと養分を蓄え、 翌年には鳥などに食べられてもなお余る実(種)をつけるという、植物たちの生存戦略だとも言われています。 私たちも、野球などのスポーツで「タメ」と言う言葉を良く耳にするように、自分の持つ力を充分に発揮するときには、 その前にそれをためることが大切なようです。「禍福はあざなえる縄のごとし」ということわざがありますが、 「禍」は「福」につながる「タメ」の時間なのだと考えることができるかもしれません。 ところで、先日、イチジクの木にかけてある防鳥ネットに「ヒヨドリ」が絡まっていたので、かわいそうだなと思い逃がしてやりました。 人になつきやすい鳥らしいので、ひそかに「ヒヨドリのおんがえし」も期待していたのですが、 今朝イチジクの収穫に行ってみると、近くの木からヒヨドリが集団で逃げていきました。 どうも、彼は、友達を連れて恩返しに来たようです。(T)   |
令和2年8月27日 |
|---|
|
あかあかと日はつれなくも秋の風 5時ちょうどに起きて、軽く新聞に目を通す。そして、玄関の花と畑の野菜に水やりなどをし、台所の野菜くずを「コンポスター」に入れて、ぐるりぐるりと。 つぎに、庭池の鯉・睡蓮鉢のメダカ・水槽のヨシノボリ(ゴリの仲間)に餌をやり、シャワーで汗を流し、インスタントコーヒーを傍らにギターを弾く.....。 これが、朝のルーティーン。出勤までの2時間半ほどは、私にとっては、ちょっとした至福の時間でもあるのですが、また、いろいろなことで「季節」を感じることができる時間でもあります。 先日は、畑で水やりをしていたときに、首筋に感じた風に はっ としました。昨日までとは違った、ひんやりとした涼風です。 立秋が過ぎたあと、文字通りの残暑が続く毎日に、少々辟易していたのですが、やはり「秋」は、しなぁーっ と近づいて来ているようです。 『古今和歌集』には「秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる」という歌もありますが、私は、『おくのほそ道』に収められている冒頭の句が好きです。 日に照らされながらてくてく歩いていた芭蕉が、ふと立ち止まり、笠をかしげて空を見上げる姿が思い浮かびます。 暑い最中の、登下校にマスク。日々の生活にも少々疲れ気味で、「こんな夏休み、はやく終わらんかなぁ」なんて、妙な感覚に襲われている人もいるかもしれませんね。 でも、それも、もう少しの辛抱かも.....。もっとも、昔は、よく受験生諸君に「あのねぇ、秋の虫が鳴き始めると、本当にあせるんだよぉー」などと言ってたんですがね。(T)   |
令和2年8月3日 |
|---|
|
「末は博士」だったかもしれない アマガエルが雨宿りしそうだった梅雨も、ようやく明けましたね。 8月になって、「もう夏休み」のはずが、「まだ授業」というところも多いのではないでしょうか。 高校生は「補習が授業になっただけ」などと割り切っているかもしれませんが、 小学生は「今年は夏休みが減った」なんて残念に感じているかもしれません。というわけで(?)、小学校時代の思い出話をひとつ。 中学校までは、理科の実験が大好きでした。数学の計算は嫌いだったけど、理科に出てくる計算をするのは嫌いではありませんでした。 小学校の時に科学雑誌を定期購読していたのですが、月に一度届く雑誌の「ふろく」がとても待ち遠しかったのを覚えています。 そして、『サンダーバード』に出てくる『ブレインズ』みたいな科学者がかっこいいなぁと思いながら、自分でもよく「実験」をしていました。 その頃、『象が踏んでもこわれない』という筆箱がありました。テレビのコマーシャルでは、たくさん並べられた筆箱の上を本物の象が歩くのですが、ひとつも壊れないんです。 ある日、どうしてもそれが欲しくなった私は、耐久性という点でいかにコストパフォーマンスに優れた製品であり、 手にすることがいかに自分の学習の充実につながるのかを母親に力説し、どうにかこうにかお小遣いを得ることができました。 翌日の放課後、喜び勇んで文房具店であこがれの逸品を購入した私は、家路をたどりながら自分でもその強度を試そうと考え、 自室に戻り、まず、椅子の上からそうっと上に乗ってみました...大丈夫です! なので、強度実験の第2段階として、今度は椅子の上からすこし飛び降りてみたのです。が...なんと、 「ぱきっ」という音とともに、ふたの中央部に亀裂が生じてしまいました。 そして、その日の夕方、帰宅した母親から買った筆箱を見せろと言われ、案の定こっぴどく叱られてしまいました。 つまらないことをして、大切なお金を無駄にするなと...。 高校では、理科嫌いになりました。数学にいたっては、因数分解ができず、思考回路が空中分解してしまいました。 そして、高校卒業後は歴史の道に進むことになりました。歴史学では、「もし」を問うことは批判されがちなのですが、 ...もし、あのとき母親が「象が踏んでも壊れないのに、なんで、あなたが乗ったら壊れたの?」と訊いてくれていたら、 「科学の道に進んでいたかもしれない」などと、未だに親不孝なことを考えています。(T)   |
令和2年7月6日 |
|---|
|
ごんぎつね 雨の日が続いています。梅雨らしいと言えばそれまでですが、大雨の被害も出ており、そろそろ降り止んでほしいところです 畑の野菜にとっては、今のところは「恵みの雨」なのか、我が家では、連日キュウリの収穫ができています。そして、食べきれるくらいの分量を、お隣にお裾分けしています。 直接手渡せたときに「この前もらったの、おいしかったぁ!」などと言ってもらえると、ちょっと嬉しくなりますね。 留守だったときは、「喜んでくれるかなぁ」と心配しながら、そっと玄関に置いておきます。ふと、「『ごんぎつね』みたいだなぁ」と思ってしまいます。 自分がしたいたずらのつぐないに、母をなくし独りぼっちになった「兵十」の家にいろんなものを届ける、小ぎつねの「ごん」。 毎日、栗やキノコを持って行くのですが、兵十が自分ではなく「神さま」に感謝しているのを知って、「つまんないな」と思ってしまいます。 この物語の最後では、栗を持って行ったところを兵十に見つかったごんが、いたずらをしに来たのだと勘違いされて、鉄砲で撃たれてしまいます。 そして、土間に栗が置かれているのを見た兵十から、「おまえだったのか、いつも栗をくれたのは」と言われ、ぐったりと目をつぶったままうなづきます。 きっと兵十を思い遣る自分の気持ちをわかってもらえて、嬉しかったのだろう思います。 今年になって、それまで挨拶程度だった近所の方と、いろんな交流ができるようになりました。これも、野菜や花を育て始めたおかげです。 栽培のノウハウだけではなく、今まで私があまり気を回してこなかった「在所」のことも話題になります。 昔「○○のおじちゃん」「☆☆のおばちゃん」と呼んでいた方たちの近況や、今の子どもたちの様子。 一人暮らしのお宅も多いのですが、皆さん「お裾分け」や「差し入れ」をしながら、お互いのことを案じているのがわかります。 本当に嬉しいのは、「良かったら、これ、食べて!」という言葉に、「思いやりの心」が感じられたときなのだろうと思います。 私も、ちゃんと「心のお裾分け」ができているのか、ちょっと心配になってきました。でも、キュウリを持って行ったときに、鉄砲で撃たれるようなことは、多分ないと思います。(T)   |
令和2年6月11日 |
|---|
|
雨がやんだら 久しぶりに、「まとまった雨」が降っています。このところの「高温・乾燥」と戦っていた植物たちにとっては、まさに恵みの雨といったところでしょうか。 野菜作りが上手な裏のO家のおばさんも、先日は「気温が33℃、土の中の温度は45℃だったよ」とこぼしていましたが、今日はきっとほっとしていることでしょう。 どれだけ朝晩の水やりをしていても、やはり「自然の雨」は違いますね。 前回雨が降ったときは、翌朝、野菜たちがいつも以上に「くいっ」とひと伸びしているのがわかりました。 ところで、我が家では、今年から野菜作りを始めました。昨年、たぬきと「仁義なき戦い」を繰り広げた土地などを畑にして、 タマネギ・スナップエンドウ・キュウリ・トマト・ナス・スイカ・メロン・ジャガイモ・サツマイモ・ネギ・青ジソ・トウモロコシ・二十日だいこんを植えました。 野菜作りは「ど素人」の私ですが、裏のおばさんからアドバイスをもらいながら、なんとか頑張ってやっています。 これまでに、スナップエンドウと二十日だいこん、タマネギの収穫と、ジャガイモの「試し堀り」をしました。 自分で育てたものを、収穫後すぐに食べると、とてもおいしく感じます。また、「お隣」にお裾分けして、喜んでもらえると、それも嬉しいものです。 ただ、タマネギを収穫した二日後に、農家をしている親戚からたくさんタマネギをもらった母親は、ひそかに途方に暮れているようです(^_^)。 この雨があがった後に予定しているのは、「メイクイーン」「キタアカリ」「インカのめざめ」の収穫です。 試し堀りした「キタアカリ」のジャガバターはとてもおいしかったので、収穫後は、他の二種類と食べ比べをしてみたいと楽しみにしています。(T)   |
令和2年4月30日 |
|---|
|
小学校時代の「走馬灯」体験 その日、私は、裏庭に放置されていたコンクリート製の「流し台」を、近所の友達と二人がかりで移動させることにしました。 その流し台は、今でも裏庭にありますが、かなり重たいものです。片側をなんとか二人で持ち上げて、ほぼ垂直に起こしたそのとき、 友達が何故か急に手を離し、流し台は私の方に倒れかかってきました。下敷きになりそうな私を見る友達の、「大変だ」という表情を、 今でも思い出します。 「えっ」と思ったその瞬間のことです。私の脳裏に、たくさんの記憶が、ものすごいスピードで、「ばぁーっ」と浮かんできました。 まるで、懐かしい映画を、一挙に、同時に、見ているような感覚です。本当に、一瞬の出来事です。 幸い、すんでの所で体をかわしたことで、怪我はしなかったのですが、とても不思議な体験として、鮮明に覚えています。 ずいぶん後になって知ったのですが、これは、人が突発的に死に直面した状況下で、走馬灯のように記憶が蘇る「パノラマ記憶」と呼ばれる現象だそうです。 あの志村けんさんが、新型コロナウイルスによる肺炎のために亡くなって、もう1ヶ月がたちます。その訃報をニュースで知ったときは、あまりにも突然で、本当にびっくりしました。 日本中の人が、「まさか」と思ったのではないでしょうか。 志村さんの追悼番組では、加藤茶さんが、「たぶん、本人もわかってないと思いますよ、死んだこと」とおっしゃっていました。 ですが、私は、きっと、笑顔にしてきたたくさんの人たちとの、走馬灯のように蘇る幸せな想い出に囲まれながらの旅立ちであっただろうと思っています。 合掌。(T)   |
令和2年3月16日 |
|---|
| 「ずぼら」のススメ? 2年とちょっと前、一念発起して、エレキギターの練習を始めました。 実は、大学時代に一度挑戦してみたことがあります。ただ、そのときは、「耳コピ」(カセットテープを聴いての練習)の煩わしさに、あっさりと挫折しました。 それに比べると、今は本当に有り難い時代になりましたね。インターネットで探せば、弾き方解説の動画や練習用の音源が見つかるのですから。 なんとか弾けるようにはなりますし、そして、ちょっとした自己満足の世界を味わうことができます。 ところで、私は、二つの曲を平行するやり方で練習をしています。 「Hotel California」という技術系の曲と、「Canon Rock 」という早弾き系の曲です。 「凡事徹底」「一意専心」、まず一曲を極めるべきなのかもしれませんが、性根を入れてひとつの曲だけを練習すると、 得てして「楽しみ」だったものが「苦しみ」へと変わり、思いどおりにできない自分に対する自己嫌悪に陥るのです。 とりあえず、「Hotel California」で心が折れたときには「Canon Rock 」に切り替えるというふうに気分転換を図りながら、ギターの練習自体はなんとか続けています。 そういう練習の仕方をしていて、ふと気づいたことがあります。技術系の練習に飽きて早弾き練習に切り替え、そしてもとの練習に戻したときに、 それまで何度やってもできなかったところが「すっ」とできちゃうことがあるんです。 その逆も、あります。ひょっとしたら、根気強く一事を極めることができない私のような「ずぼら人間」には、そういうやり方のほうが合っているのかもしれません。 ともあれ、子どもの時分から飽きっぽかったこの私が、2年とちょっとの間、ほぼ毎日欠かさずにエレキギターの練習を続けているのですから、たいしたものです。 でも、やっぱり、上達のスピードは遅いなぁ!(^_^) (T)    |
令和2年2月17日 |
|---|
| 「ありがとう」のひとこと デパートの売り場や専門店といった「高級な」ところは、あまり好きではありません。にこやかに微笑みながらいつの間にかそばにいる、あの店員さんの上品さが苦手です。 客としての資質を見定められているようで、とても緊張します。 大学時代、うっかり店員さんにぶつかってしまい、一生懸命謝っていたら、それはマネキンだったという体験があります。 というわけで、ほとんどの買い物はスーパー・コンビニや量販店・百均ショップで済ませるようになってしまいましたが、ひとつ心にとめていることがあります。 それは、レジで支払いを済ませる際に、必ず「ありがとう」のひと言を添えることです。 さっさと「用事」をすませ、当たり前のようにだまってお金を払って去って行く人を見ると、少し悲しくなります。 ところが、本来人との会話があまり得手ではない私(N町のT)は、その「ありがとう」が言えなくて、落ち込んでしまうこともあります。 相手の方に、「感謝の気持ちをどう伝えようか」と言葉を選んでいるうちに、タイミングを失ってしまって、お礼を言わずじまい .... というような。 あるとき、あまりにもそのことが気になってしまって、後日改めてその方に感謝の意をお伝えしたのですが、「ほう、やっと言うたか。 あんなときは、嘘でも良いから『ありがとうございました』ぐらいは言うもんや」と叱られてしまいました。 そうなんです。かっこいい言葉でなくても、「ありがとう」でいいんですよね。 『贈る言葉』という曲に、「はじめて愛したあなたのために、飾りもつけずに贈る言葉」という歌詞の一節がありますが、気持ちがこもっていれば、飾り気のない「ありがとう」で充分なのかもしれません。 ややもすればルーティンになりがちな、「おねがいします」「ごちそうさま」そして「ありがとう」。もう少し「心」を意識できる人間になれたらいいな、と思います。(T)   |
令和2年1月21日 |
|---|
| 飼い主の願い 今年の冬は暖冬ということで、例年になく、私達には除雪の心配もあまりなく助かりますが、スキー場では「助けてくれ~!何とか雪を・・・」とやきもきしている模様?・・・・。 さて、H市のH家では、猫を2匹飼っている。この猫達は、この家に来てそれぞれ6年と4年になる雄猫だが、お祖母ちゃんとお母さんと娘3人という、私以外には男のいない家で、とても大事にされている。 小さいときから同じように育てられてきたにもかかわらず、6年めの「シオン」くんは大人しくて抱っこが嫌いで細め。 ナイーブなのか食べ過ぎると、食べたご飯を吐いてしまって「ミャー(またちょうだい)」とおねだりするかと思えば、ちょっかいをかけに来た「弟」に猫パンチをおみまいしている短気な面も・・・。 4年目の「レオン」くんは、やんちゃで甘えん坊の大食いで太め。自分を猫と思っていないかのごとく(きっとこの家のムスコだと・・・)、手足を伸ばしてあお向けの大の字になって昼寝しているかと思えば、 毎日朝の5時から2階の出窓で外の雀と会話し(ているつもりで、キュルクル、クルル・・・・と鳴き)、果ては、私や妻の寝ている顔の上にソッと手を置き、払っても「ダメ!」と言われても、 何度でも繰り返して朝ご飯をおねだりしてくる・・・。 彼らを見ていると、一人一人(一匹一匹?)がそれぞれに自分らしさを失うことなく育ってくれていることに、なんとなく嬉しくなる・・・。頑張って生きてくれていることに微笑ましくもある。 (考えてみると娘達も何とか・・・?) 彼らのこれまでの成長に感謝し、もし今後の人生で荒波にもまれて生きることになろうとも、自分らしさと素直な心を持ち続けて歩いてほしい(娘達にも・・・。)と願うのは、年取った飼い主(親?)のいらぬお節介???・・・。 ただ、これはどの飼い主(親)も思うことでは・・・。 まあまあ、「小賢しいやつだ」「ウザい」などと言わずに、たまには聞いてやって下さい。涙もろくなってきた年寄りの、年の初めの独り言。(H)    |
令和2年1月6日 |
|---|
| つかのまの団欒 新年おめでとうございます。 例年より「休み」が長かったこの年末年始、どのようにお過ごしでしたか。 少しは、ご家族でのんびりされたでしょうか。というわけで、N町T家の親子団欒のひとこまをご紹介します。 娘の部屋から電子ピアノで弾く「Let it be」が聞こえてきたので、ギターとアンプを持って行ってセッションをしました。 初めはお互いに演奏したり伴奏したりしていたのですが、そのうち「 Let it be と Let it go(アナ雪)のサビの部分のコード進行はほとんど同じ」という話になりました。 その時、私は思わず「パッヘルベルが作曲した『カノン』のコード進行を使っている曲も多いのだよ。クリスマスイブ(山下達郎)、揺れる想い・負けないで(ZARD)、 TOMORROW(岡本真夜)、少年時代(井上陽水)、勇気100%(光GENJI)、とかね」と格好つけて余計なうんちくを傾けてしまいました。よせば良いのに。 それを聞いた娘は、「それじゃその曲をメドレーでやってみるから伴奏して」と。そして、音を拾いながら、それぞれのメロディーを弾き始めました。 おかげで私は、カノンのコードを、D・A・Bm・F#m・G・D・G・A ~ ~ ~ と繰り返し繰り返し、ひたすらギターを弾き続ける羽目になりました。 後悔先に立たず。終いには指版を押さえる左手が痛くなり、「負けないで」の歌詞の一節を身をもって実感することになりました。 とはいえ、普段は忙しくてほとんど会話らしい会話が出来ない娘と、楽しいひとときを過ごすことが出来ました。ありがと、ありがと。(T)   |
令和元年12月24日 |
|---|
| 便利さと豊かさ 「三種の神器」や「3C」という言葉があります。 1950年代後半の神武景気の頃、「白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫」が「三種の神器」と呼ばれ、豊かさやあこがれの象徴でした。 そして、高度成長期となった1960年代半ばには、「カラーテレビ・クーラー・自動車」が「3C」と称され、 それらが備わっていることが中流家庭であることの象徴とされていました。 それから一時代が過ぎた、1970年代半ば頃の我が家(N町のT家)のことです。ある日、私の両親が「おいしいと評判の中華料理店へ行こう」と言い出しました。 むろん私に、異論などありません。私は「我が家はとても金持ちとは言えないが、まあ中流程度の暮らしは出来ている」と感じていましたが、 それまで本格的な中華料理というものを食べた記憶はなかったのです。 その日私は、中流家庭にふさわしい贅沢への大きな期待と、中華料理の作法に対する少しばかりの不安を胸に、両親の後に続いて中華料理店「S」に入りました。 そして、テーブル席に着いたほぼその瞬間のことでした。両親は、品書きに目をやることもせず、こう言ったのです。「ここは味噌ラーメンが美味しいらしいよ」と。 なるほど、うまいラーメンでした。そしてそれを食べながら、私はふと我が家の現実に気づいたのです。カラーテレビはあるが、あとの二つの「C」は無いなと。 ただ、確かにご近所に比べ当時の我が家には「話題のもの」「最新のもの」はなく、「便利」ではありませんでしたが、 両親・祖父母との3世代が楽しく過ごす家族であり、そういう意味では「豊か」だったなぁとも思います。 先日、「AI(人工知能)」「4K(超高精細画像)」「5G(次世代移動通信システム)」が令和時代の三種の神器の「キーワード」なのだというネットの記事を見つけました。 これらの搭載・対応・接続などによって、より生活に便利なモノやシステムが生まれるようです。 これまでのような「生活に便利なテレビや自動車があるか」ではなく、「どんなテレビや自動車であればより生活が便利になるか」という概念です。 ますます生活が便利になるであろう令和の時代、心が豊かになる三種の神器ができれば良いですね。令和元年も、もうあと数日。良いお年を。(T)    |
令和元年12月9日 |
|---|
| 大学ラグビー早明戦 少し前の話になりますが、テレビで早稲田大学対明治大学の試合を観戦しました。 関東大学ラグビー対抗戦では、「12月最初の日曜日」の「早明戦」が最後の試合と決まっており、 以前は、この一戦だけが国立競技場で行われて人気のカードでした。 今年の早明戦は、「らしさ」を発揮できた明治大学が、それができなかった早稲田大学に勝利しましたが、 観戦しながら、思わず東京で過ごした学生時代のことを思い出しました。で、その思い出話をひとつ。 「自分の飲食代のために」と始めた、週二回の居酒屋さんでのアルバイト。 「親父さん」は沖縄の宮古島出身で、終戦後の少年時代は、一日にサトウキビ畑の仕事などいくつもの仕事を掛け持ちして家計を助けていたそうです。 中学卒業後上京して飲食店で修行を積み、苦労に苦労、倹約に倹約を重ね、やっと自分の店を持った親父さんにしてみれば、私などはさぞかし「世間知らずの若造」に見えていただろうと思います。 私とは違い、「世間という大学」で勉強してきた親父さんは、お店の老若男女すべてのお客さんから愛され、英語は話せないのに近くに住んでいた外国人たちともなぜか楽しく会話が出来ていました。 おかげさまで、私もそこで「実践英会話」を学ばせていただきました。 その親父さんが、ある時とても憤りながら、私達アルバイトを諭してくれたことを思い出します。 「隣の喫茶店のアルバイト学生が、お金のことを『カネ』って言うんだよ。一生懸命に働いてもらったお金じゃないから、お金の有り難みがわからないんだ。そんな奴には、周りの人たちの有り難みだってわかるはずないよ」と。 大学卒業後、何度かアルバイト先に行き女将さんとは会いましたが、新しく出店した店の方を切り盛りしていた親父さんとは会えずじまい。 大学ラグビーの試合を観たら、親父さんの懐かしい笑顔を思い出してしまいました。(T)  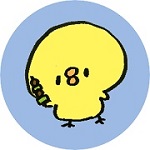 |
令和元年11月12日 |
|---|
| 続 令和たぬき合戦 たぬきとN町T家の土地争いは、新しい局面をむかえています。 「科学兵器」を導入して以降、大規模な「ふん害」はなくなりましたが、「ちょっとは私らへの配慮も必要でしょ」的な「意思表示」は時々見られていました。 しかし、土地所有者としての威厳は、後々のためにもしっかりと彼らに示さねばなりません。 そこで、毎朝地面に残された足跡をもとに彼らの通行経路を解析し、侵入口と思われる付近の防御体制(防鳥ネットの再利用による迎撃システム)を構築しました。 それ以降、畑を横切るような大胆不敵な行動は見受けられません。「私たち端っこ歩きますから」的な「遠慮がちな気持ち」が感じられます。 ただ、新たに気づいたこともあります。それは、彼らのものとは違う小さな足跡の存在です。 いつも野菜作りで助言をいただいている裏のO家のおばさんの話によれば、どうもそれは「同じくこの辺りを縄張りにしている『ハクビシン』と『こげ茶のネコ』の可能性が高い」とのこと。 今後は、近隣のおばさんたちと野生動物および野良猫に関する情報交換を継続しつつ、ひきつづき彼らの行動を注視したいと考えています。(T)    |
令和元年10月11日 |
|---|
| 秋祭り 地区の獅子舞連の相談役から声をかけられ、練習に参加しました。 子ども会の世話をしていた頃に、その縁で囃子方として笛を担当して以来、約10年振りの獅子舞練習です。 参加してみると、当時小学生で囃子方として鉦や太鼓を担当していた子どもが踊り手(天狗)になっており、 毎朝通学時に顔を合わせる小学生たちが囃子方として新たに獅子舞連に加わっていました。 また、10年前に踊り手だった青年たちは、一回りも二回りもたくましくなり、重鎮の方々と一緒になってリーダーシップを発揮していました。 小さな「在所」ではあるけれど、世代を超えたチームワークによって地域の伝統が脈々と繋がっていくように感じられ、とても嬉しく思いました。 残念なことに当日は雨のために「宮祭り」となり、獅子舞は中止になったのですが、短い期間とはいえ「伝統を継承する」という作業はとても楽しい体験でした。 もうひとつ、良いことがありました。顔なじみとなった子どもたちとの「おはようございます」の挨拶に、明るく元気な笑顔が加わったことです。(T)   |
令和元年10月1日 |
|---|
| 令和たぬき合戦 我が家(N町のT家)では、ここ二週間ほど、たぬきとの交戦状態が続いています。 事の発端は、畑を作ろうと、数年間放置していた30㎡ほどの空き地を耕したことに始まります。おそらく、夜な夜なその辺りを徘徊していたであろうたぬきどもは自分たちの縄張りを侵されたと考えたのでしょう。彼らはいきなり「土地の所有権」を主張し始めたのです。土地名義人として固定資産税を支払っている身としては、その「フン害」に対していたく憤慨し、「負けてはならぬ」と徹底抗戦を決意したのです。 何度かの交戦ののち、たぬきの侵入を感知して超音波・LED発光・ブザーを作動させる新兵器を導入するに至りました。それ以来、足跡は一度見かけたものの、フン害はなくなりました。 今のところ、私達の科学(かがく)が彼らの化学(ばけがく)を凌駕する形になってはいますが、次の一手を用意しておく必要もあると考えています。インターネットで調べた情報によれば、「オオカミや大型犬の尿」が効果的らしいのですが、生憎、私の近所にはオオカミや大型犬はいません。 ラグビー、バレーボール、陸上競技.....W杯や世界選手権では、アスリートたちによる素晴らしい戦いが繰り広げられているのに、レベルの低い争いごとの話で、どうもすみません。(T)   |
令和元年9月24日 |
|---|
| 昨日の台風、大丈夫でしたか? 三連休最終日の昨日は、台風の影響で風の強い一日となりました。被害はありませんでしたか?。台風一過の今日は、残念ながら「すっきりとした秋晴れ」という訳にはいきませんでしたが、ひいやりとした空気に秋の深まりが感じられる一日となりました。 季節の変わり目です。秋は、「寝冷え」によって引き起こされる風邪や腹痛などの症状が、最も多い季節なのだそうです。どうか、お気をつけください。 9月21日から、秋の全国交通安全運動が実施されています。交通ルールをまもり、正しい交通マナーの実践を心がけましょう。(T)   |
令和元年9月19日 |
|---|
| 最近、日が暮れるのが早くなりましたね。 秋は夕暮れ。夕日の差して山の端いと近うなりたるに、からすの寝所へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへあはれなり。 まいて雁などの連ねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入りはてて、風の音、虫のねなど、はたいふべきにあらず。(清少納言「枕草子」) 数学者の藤原正彦さんの著書『国家の品格』に、自宅に招いたアメリカ人の大学教授が、庭で鳴く「虫のね」を聞いて「何だあのノイズは?」と言ったというエピソードが紹介されています。 日本人と欧米人、わたしとあなた。感性は、民族によって、人によって、世代によって、違うものであるようです。(T)   |
令和元年9月13日 |
|---|
| 今日は「中秋の十五夜」です。 天気予報によれば雨の心配はなさそうなので、「中秋の名月」がとても楽しみです。お月様といえば「ウサギ」ですが....こんなインド神話があります。 昔、あるところにウサギとキツネとサルがおりました。ある日、3匹は疲れ果てて食べ物を乞う老人に出会い、サルは木の実を、キツネは魚をとってきました。しかし、ウサギは一生懸命頑張っても、何も持ってくることができませんでした。そこで悩んだウサギは、「私を食べてください」といって火の中にとびこみ、自分の身を老人に捧げたのです。実は、その老人とは、3匹の行いを試そうとした帝釈天という神様でした。 帝釈天は、そんなウサギを哀れみ、月の中に甦らせて、皆の手本にしました。 月面の低地の「暗い影の部分」が何に見えるかは国や地域・民族によって違うのですが、日本・中国・韓国・アメリカ先住民・メキシコでは「ウサギ」なのだそうです。ちなみに、モンゴルでは「犬」、カナダでは「女性」、アメリカでは「女性の横顔」。 う~~む。(T)   |