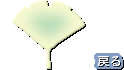金沢へ行つた人は、是迄大抵その風土、風俗、人気、飲食物などを讃めるが、私も年取つてからは好きになつた。室生君に案内された芥川君は、兼六公園のみよし亭(?)といふ処に数日滞在してゐたらしいが、昔の前田家の庭園であつた此公園の造庭術についての感心の仕方は、芥川君にさういふ教養があつたからで、旅客の皆んなが皆んなあの公園が解る訳ではない。
 私なども解らない一人である。京都辺の庭についても同じである。しかし温泉場の規模や料理の善し悪しくらゐは、少し旅でもしつけた人には比較論くらゐは出来る。食べ物のことは、最近或る雑誌に少し書いたから、簡単にしておくが、嘗つて巌谷小波氏は金沢へ旅をして旅館の燻しのかゝつた造作とか、床の軸物、屏風、食器類などは勿論、料理も他の地方には見られない洗練されたものがあると言つて、氏は京都の文化にお馴染が深いだけに其れに似通つた金沢にも感心してゐた。同じ金沢人でも私は少し無風流な方で、金沢の料理も、お国自慢の人ほど感心しない方で何と言つても本場には敵はないと思ふのだが、しかし到る処に数知れずある料亭のうち、どんな家へ飛びこんでもさう乱暴なものは食べさせないことだけは確かで、どんな手軽な家でもちやんとして茶庭に苔が蒸してゐて、筧の水くらゐはちょろちょろしてゐる。風呂も三条の旅館風のものがある。
私なども解らない一人である。京都辺の庭についても同じである。しかし温泉場の規模や料理の善し悪しくらゐは、少し旅でもしつけた人には比較論くらゐは出来る。食べ物のことは、最近或る雑誌に少し書いたから、簡単にしておくが、嘗つて巌谷小波氏は金沢へ旅をして旅館の燻しのかゝつた造作とか、床の軸物、屏風、食器類などは勿論、料理も他の地方には見られない洗練されたものがあると言つて、氏は京都の文化にお馴染が深いだけに其れに似通つた金沢にも感心してゐた。同じ金沢人でも私は少し無風流な方で、金沢の料理も、お国自慢の人ほど感心しない方で何と言つても本場には敵はないと思ふのだが、しかし到る処に数知れずある料亭のうち、どんな家へ飛びこんでもさう乱暴なものは食べさせないことだけは確かで、どんな手軽な家でもちやんとして茶庭に苔が蒸してゐて、筧の水くらゐはちょろちょろしてゐる。風呂も三条の旅館風のものがある。